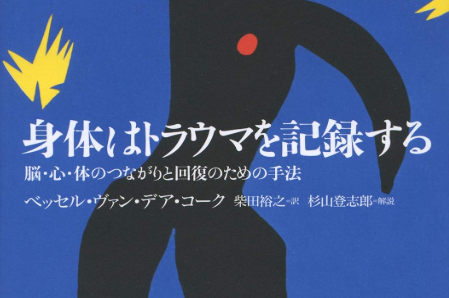人はなぜ“緑の香り”を好むのか
森に入ったとき、ふっと鼻に入ってくる「緑の香り」。多くの人は「ああ、気持ちいい」と思うでしょう。でもそれって偶然じゃなくて、人間の体が「安全で安心できる」と感じる本能的なサインなのです。
実はこの香りの正体は、樹木や草が出す フィトンチッド と呼ばれる揮発性物質です。フィトンチッドは木々が自分を守るために放つ“天然の防御ガス”みたいなもの。細菌や害虫から身を守るために放出してるのに、人間がそれを吸うと 血圧を下げたり、ストレスを和らげたりする効果 があることが研究で分かっています。
ちょっと不思議ですよね。木が「自分を守ろう!」って出した物質を、人間が「気持ちいい〜」ってリラックスに使ってるんだから。ある意味、森は天然のアロマディフューザー。
さらに、森には新鮮な酸素が満ちています。山や林で深呼吸すると「空気がおいしい!」って思う人が多いのは、酸素濃度や湿度、温度が体に心地よいバランスだから。都会のエアコンの風とはまるで違う。例えるなら、コンビニのペットボトルの水と、山で飲む湧き水くらいの差です。
もうひとつ面白いのは、緑の香りを嗅ぐときに働く 副交感神経 の作用です。副交感神経は「休息モード」のスイッチで、森の香りはこのスイッチを自然に入れてくれる。だから森に行ったとき「何もしてないのに肩の力が抜ける」なんてことが起こるんですね。
人間は太古の昔から自然の中で暮らしてきました。その長い歴史の中で「緑の匂い=命を守れる環境」という感覚を身体に刻み込んでいる。だからこそ現代人も、アスファルトの街を歩いて疲れたときに、ふと緑の匂いを嗅ぐと “ここにいていいんだ” という安心感が湧いてくるのです。
それでも嫌いと感じる人もいる
「森の匂いは癒される!」と感じる人が大多数ですが、中には「いや、むしろ苦手」と言う人もいます。意外ですよね。人間は自然が好きなはずなのに。でも実はこれにもちゃんと理由があります。
ネガティブな体験との結びつき
香りというのは、脳の中で 記憶と感情をダイレクトに結びつける 特性があります。たとえば焼き立てのパンの匂いを嗅いだら、小学校の帰り道のベーカリーを思い出して懐かしくなる、とか。これと同じで、「森の匂い=嫌な記憶」に繋がってしまう人もいます。
湿気でジメジメした思い出、虫に刺されてかゆかった体験、あるいはキャンプで大失敗した記憶――。そういう記憶が積み重なると、森の匂いを嗅いだ瞬間に脳が「また嫌なことが起こるかも!」と警戒してしまう。だから「落ち着く」どころか「不快」と感じてしまうのです。
嗅覚の敏感さ
もうひとつの理由は 嗅覚の個人差 です。人間の嗅覚って、実は視力や聴力以上に個人差が大きいもの。敏感な人はほんの少しのカビ臭さや湿った土の匂いまでキャッチしてしまう。結果として、周りの人が「気持ちいい!」と言ってても、自分は「ムッとする」「頭が重い」と感じてしまう。
これは自律神経のバランスとも関係しています。香りが刺激として強く入ると、交感神経(活動モード)が優位になって「休まるどころか疲れる」という現象も起きます。こうなると森の香りが「癒し」ではなく「ストレス」になってしまいます。
好みの違い
最後はシンプルに、ただの 好み。食べ物で「私はコーヒー大好き!」って人もいれば「苦くて無理!」って人がいるのと同じで、香りにも向き不向きがあるんですね。「みんな好きなはず」と思いがちな森の匂いも、個人差で嫌われることは全然自然なこと。
まとめると、森の匂いを嫌う人の理由は
- 過去のネガティブな記憶
- 嗅覚の敏感さや自律神経の反応
- 単純な好みの違い
この3つが主な原因。
だからもしあなたの周りに「森の匂い苦手なんだよね」という人がいたら、「えっ変わってる!」と思うかもしれませんが、その人の感覚がそういう風に働いてるだけで、ちゃんと理由があることなのです。