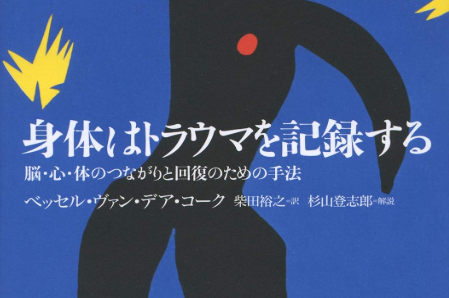1. なぜこの本が注目されているのか
『身体はトラウマを記憶する』(原題 The Body Keeps the Score)は、精神科医ベッセル・ヴァン・デア・コークによるトラウマ研究の集大成です。世界的なベストセラーとなり、心理学や精神医療の専門家だけでなく、一般の読者にも広く読まれています。
なぜここまで注目を集めているのでしょうか。理由はシンプルです。
- トラウマは心の問題ではなく「体」に刻まれる という視点を明確に示したこと
- 脳科学や臨床研究の知見をもとに、従来のカウンセリングや薬物療法だけでは不十分である理由を示したこと
- そして、回復のためには「体に働きかける方法」が必要だと、多様なアプローチを紹介していること
従来、トラウマは「心の傷」として語られることが多く、会話や思考で癒やすことが中心でした。しかしこの本は、「体が危険を記憶し続けるために、不安やフラッシュバックが止まらない」という現実を科学的に解き明かしました。
そのため、「薬もカウンセリングも効果を感じられなかった」という人々にとって、大きな希望となっています。単なる理論書ではなく、「どうすれば癒しにつながるのか」という実践的な指針を与えてくれるのです。
2. トラウマは体に刻まれるとはどういうことか
多くの人は「トラウマ=心の問題」と考えます。過去の出来事を思い出すと苦しくなる、感情が揺さぶられる――そうした反応は「心の中の傷」として理解されがちです。
しかし、『身体はトラウマを記憶する』が明らかにしたのは、トラウマは頭の中だけで起きているのではなく、体全体に刻まれる現象だということです。
過去が「今ここ」で再現される
トラウマ体験の記憶は、ふつうの記憶のように「過去の出来事」として整理されません。海馬(記憶を時系列に整理する役割)がうまく働かないため、記憶が断片化し、体験が「現在進行形」として蘇るのです。
その結果、フラッシュバックや悪夢が起こり、心臓の高鳴りや呼吸の乱れ、筋肉の緊張などが「その場で再び危険にさらされている」かのように体に走ります。
理屈では止められない体の反応
「もう安全だ」と頭で理解しても、体は別の反応をします。
- 扉がバタンと閉まる音に過敏に反応してしまう
- 特定の匂いや光景に突然緊張する
- 他人のちょっとした表情や声に過剰に怯える
こうした反応は意思の力では抑えられません。体の中に「危険はまだ終わっていない」という記憶が残り続けているからです。
トラウマは「体の記憶」
この本が強調するのは、トラウマを解消するには「言葉や思考だけに頼るのでは不十分」ということです。体に残された緊張や警戒心に直接アプローチし、神経系を「安全モード」に戻す必要があります。
つまり、トラウマは「心の病」ではなく「心身全体の反応のズレ」。だからこそ、呼吸・ヨガ・瞑想・身体表現など、体を介したアプローチが癒しの鍵になるのです。
3. 脳と神経系に起きる変化
『身体はトラウマを記憶する』の中で詳しく解説されているのは、トラウマが脳と神経系にどのような影響を与えるかです。これを理解することで、「なぜ自分の意思でコントロールできないのか」がはっきりと見えてきます。
扁桃体 ― 警報が鳴りっぱなしになる
扁桃体は、危険を察知して瞬時に体を守る「警報装置」のような役割を持っています。
トラウマを負うと、この扁桃体が過敏化し、わずかな刺激にも「危険だ!」と反応するようになります。ドアの音、誰かの視線、匂い、わずかな変化で過剰にアラームが鳴ってしまうのです。
前頭前野 ― 理性のブレーキが効かない
通常なら前頭前野が扁桃体の反応を抑え、「それほど危険ではない」と判断してくれます。ところがトラウマを抱えた人では、前頭前野の働きが弱まり、理性のブレーキがかかりにくくなります。結果として、怒りや恐怖がそのまま表に出やすくなります。
海馬 ― 記憶を過去に整理できない
海馬は出来事を時系列に整理し、「過去のこと」として保存する役割を担っています。トラウマ時には海馬の働きが低下し、記憶が「今起きていること」として再体験されます。これがフラッシュバックや悪夢の原因です。
自律神経 ― 緊張が続く身体
扁桃体が危険信号を出し続けると、自律神経のうち交感神経(戦う・逃げるモード)が常に優位になります。心拍数上昇、筋肉の緊張、呼吸の乱れ、発汗などが続き、体は常に警戒態勢に置かれます。
ホルモン ― アドレナリンとコルチゾール
さらに、ストレスホルモンであるアドレナリンやコルチゾールが過剰に分泌されます。これは短期的には身を守るために必要ですが、慢性的に続くと心身の疲労を招き、不眠や免疫力低下、慢性疲労などの二次的な問題につながります。
4. トラウマを抱えた人に現れる症状
トラウマは「過去の出来事を思い出すとつらい」だけにとどまりません。脳と神経系が変化することで、心や体にさまざまな症状として表れ、日常生活を大きく制限してしまいます。『身体はトラウマを記憶する』では、代表的な症状がいくつか取り上げられています。
フラッシュバック
突然、過去の記憶が「現在の出来事」として蘇り、恐怖や痛みを再体験してしまう現象です。映像のように鮮明に蘇る場合もあれば、体感として感じる場合もあります。匂いや音といった些細な刺激で誘発されることが多く、自分でコントロールできません。
過覚醒(ハイパーアラウザル)
常に体が緊張している状態です。
- 心拍数が速い
- 眠れない
- 小さな物音に過敏に反応する
- イライラしやすい
これは体が「危険はまだ続いている」と思い込んでいるために起こります。
感情の鈍麻(感情麻痺)
過剰なストレスにさらされ続けると、逆に「何も感じない」状態になることもあります。喜びや楽しみを感じられず、人間関係が希薄になり、生きる意味を見失ってしまうことがあります。
身体症状としての現れ
トラウマは心だけではなく、身体症状として現れることもあります。頭痛、胃痛、慢性的な疲労、筋肉のこわばりなどがその例です。医療機関で検査しても原因が見つからず、「心のせい」と言われてしまうこともありますが、実際には神経系の緊張が体に反映されているのです。
人とのつながりの困難
トラウマは人間関係にも深刻な影響を及ぼします。誰かを信じることが難しくなったり、親密な関係を避けたりする傾向が強まります。安全であるはずの関係さえ危険に感じてしまうのです。
5. 従来の治療の限界
長い間、トラウマの治療は主に カウンセリング(会話による治療) や 薬物療法 に依存してきました。これらは確かに効果をもたらす場合もありますが、『身体はトラウマを記憶する』では、それだけでは十分ではないと指摘されています。
カウンセリングの限界
カウンセリングや心理療法では、言葉で過去の出来事を整理し、認知を変えることで苦しみを和らげようとします。しかし、トラウマは「言葉にならない記憶」として体に残ることが多いため、話すだけでは解消できないことがあります。むしろ思い出すことで再び強烈な感情が蘇り、症状が悪化することもあります。
薬の限界
抗不安薬や抗うつ薬は、不安や不眠などの症状を一時的に和らげる効果があります。しかし、根本的にトラウマの記憶や身体反応を消すことはできません。さらに副作用の問題や、効果が限定的なことも少なくありません。
「頭」だけに働きかけても不十分
最大の問題は、これら従来の治療が「頭=思考や感情」に偏っている点です。トラウマは脳だけでなく、体、神経系、感覚に刻まれています。だからこそ、「もう安全だ」と頭で理解しても、体は過去の危険を再体験し続けてしまうのです。
この本が示すのは、トラウマを解消するには体にも働きかけるアプローチが不可欠だ ということです。
6. 癒しの鍵 ― 体に働きかける実践
『身体はトラウマを記憶する』が大きな反響を呼んだ理由のひとつは、従来の「話すこと」「薬を飲むこと」中心の治療に加えて、体に直接アプローチする方法の重要性 を示した点にあります。トラウマは体に刻まれるため、回復のためには体を通した新しい経験が不可欠なのです。
呼吸法
呼吸は自律神経に働きかけるもっとも身近な方法です。吸う・吐くのリズムを意識的に調整することで、過覚醒状態から副交感神経を優位にし、体を落ち着けることができます。
ヨガや瞑想
ヨガは体の感覚に注意を向ける練習でもあり、「体を再び自分のものとして感じる」体験を取り戻す助けになります。瞑想は「今ここ」に意識を戻し、過去に引きずられる脳のパターンを少しずつ変えていきます。
ダンスや演劇などの身体表現
リズムに合わせて体を動かすこと、声を出すこと、表現することは、言葉にならない感情を解放する手段になります。音楽療法やドラマセラピーも、こうしたアプローチのひとつです。
EMDR(眼球運動による脱感作療法)
専門的な技法ですが、目の動きに合わせて脳の処理を助けることで、トラウマ記憶を「過去のもの」として整理できるように導きます。
安全な人間関係の中での体験
体に働きかける実践と並んで重要なのが「つながり」です。信頼できる人との関係性の中で安心を体験することが、神経系に「危険は終わった」と知らせる最も自然な方法でもあります。
7. まとめと読者へのメッセージ
『身体はトラウマを記憶する』が伝えているのは、トラウマが「心の弱さ」ではなく、体と神経系に刻まれた防御反応 だという事実です。だからこそ、頭で「大丈夫」と理解しても、体は危険に備え続けてしまうのです。
しかし同時に、この本は希望も与えてくれます。
呼吸、ヨガ、瞑想、身体表現、人とのつながり――体に働きかける方法を通じて、私たちは再び「自分の体を安心できる場所」として取り戻すことができるのです。
回復は一瞬で起こるものではありません。けれど、小さな実践の積み重ねが、やがて大きな変化につながります。呼吸を整え、体を感じ、安全な関係性を築くこと。その一歩一歩が、トラウマに閉ざされた人生を少しずつ解き放っていきます。
もし今、薬やカウンセリングで効果を感じられずに行き場を失っているなら、この本の視点は新しい希望になるはずです。そして、あなた自身ができる小さな実践が、回復への扉を開いてくれます。
👉 興味を持った方は、ぜひ ベッセル・ヴァン・デア・コーク著『身体はトラウマを記憶する』 を手に取ってみてください。
➡ Amazonで詳細を見る
※当サイトはAmazonアソシエイト・プログラムの参加者です